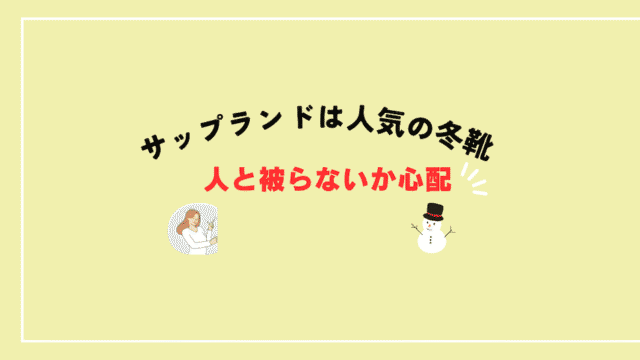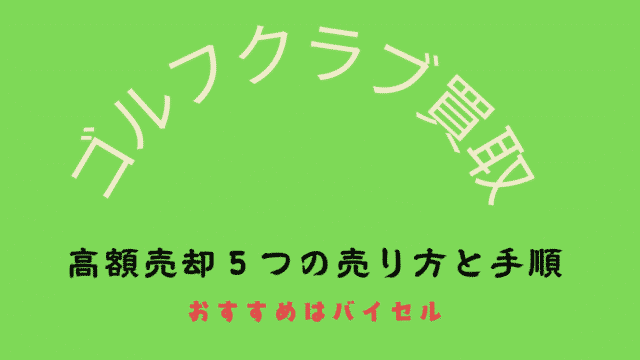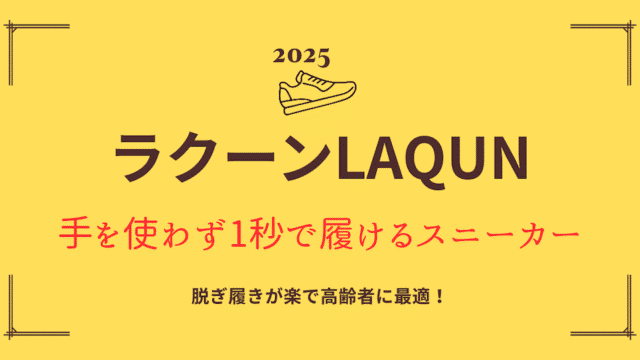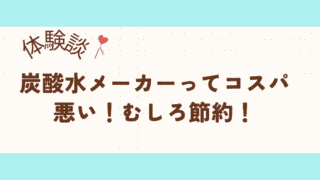昨年からジワジワとはじまった「令和の米騒動」
いまや、日本全国に大きな影響を及ぼしています!
いつもは、そんなに売れてない商品がバズったり
昔から実直に商売していた老舗のメーカーが廃業したり
もちろん、わたしたち一般消費者のお財布も圧迫!
7月19日(土)放送予定の「所さん!事件ですよ」では「令和の米騒動に端を発する」こういった問題を取り上げるようです。
引用元:「所さん!事件ですよ」番組公式サイト
本記事は、今回放送予定の番組の内容予想から
令和の米騒動の「トピック、意外な影響、今後一体どうなるのか?」を考えてみます
なぜ米高騰で「ふりかけ」が爆売れ?意外な消費者心理
お米が高くなっているのに、「ふりかけ」が売れる理由は
物価高騰による節約志向!
おかずなしで、「ふりかけ」だけで食べられるから!
なぜ「ふりかけ」が人気なのか!節約志向が要因?
物価高が一つの要因
米騒動でお米も高騰
お米を食べるための「ふりかけ」がなぜか?逆に人気に火がついた!
消費者の節約の気持ちが高まっていったところに、「ふりかけ」と言う手軽でお安いご飯のお供が受け入れられた
人気の理由
・1袋が100円ちょっとで買える、スーパー、コンビニで手軽に手に入る
・お昼は外食やめて、「ふりかけ」おにぎりを持参するようになった!
・安いのにめっちゃたくさんの種類! 自分の好きな味があって楽しい!
・訪日客がお土産に「ふりかけ」を買う
・味変がしやすい!
人気のふりかけ
❤️好きなふりかけ
- のりたま 16.5%
- さけ 15.7%
- ゆかり 12.1%
- カツオ 11.4%
🖐️ほしいふりかけ
- カレーライス
- キムチ
- うなぎ
- チャーハン
一般財団法人 国際ふりかけ協議会
ふりかけを旗頭に各地域の「産業・観光・文化」を国内外に広める活動をしています。
引用元: 国際ふりかけ協議会公式サイト:https://www.ifa-furikake.jp
🔸金賞:サムライ贅沢ふりかけ
・神田工業公式サイト
🔸銀賞:まごわやさしいふりかけ
🔸銅賞:生ふりかけ
お茶のつかさ園 生ふりかけ
昔はほとんどのメーカーは海苔が多めでほぼ同じ味だった
今は乾燥技術などの向上で味のバリエーションが増加!
いろんなテイストの再現力が爆増!
チャーハン、牛飯、キムチ、グリーンカレー、ホットサルサ、麻婆豆腐など
なんでもできちゃいますね!
駅弁メーカーの苦肉の策「米なし・かしわ飯」の衝撃
番組の予告では「かしわめし」がご飯の上ではなく、
トーストの上に「かしわめし」の具材が乗っている?!
そんな画像があります。
米高騰→パンを使おう!!??
これは番組を見てみないと、わかりませんね🫨

JR折尾駅(北九州市)の名物駅弁の東筑軒「かしわめし」が米高騰が直撃!
鶏のだしと秘伝の調味料を使った人気の美味しい駅弁ですが
いままでは国産のお米を100%使っていましたが、いまは大麦をブレンドしなんとか価格を抑えている状況
お米の価格が昨年の4月と比較し、約1.75倍になった時点で大麦を1割混ぜてなんとか原価を抑えて、現状の1000円以下の価格帯を維持している
味は変わらないように工夫し、食感も若干もっちりして、グッド😀
駅弁業界の代替食材への挑戦が続きます!
< 下は筆者のお米の最新状況の記事です、ご参考まで,,, >
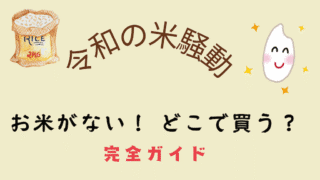
調味料・日本酒業界に迫る「第二の米騒動」の恐怖




このままでは第2第3の米騒動が起きる!
主食用米だけでなく加工用米の不足による連鎖反応が出てきています
みそ・酒メーカーの「存亡の危機」という切迫した状況になっています!
小松酒造さんの場合
原料米の高騰
日本酒を作るための、お米の価格が1俵23,000円が、30,000円を超える勢い
結果、最低で年間500万円くらいは酒米が値上げになる
商品の値上げで対応
ほぼ全商品の価格を6%引き上げ
日本酒1升瓶 約200円値上げ実施
それでも、今後はあと500円くらい値上げしないと健全な経営が厳しくなるそうです
小泉農水相の対応
酒米が高い、そして足りないと言う声に対して
約30万トンの備蓄米を酒造用・味噌などの加工用として放出することを検討
酒造好適米の山田錦などを補助金の対象とする動きもあるようです
小松酒造さんの日本酒の原料米
酒造好適米を使っているのは15種類のうち13種類、うち一般的な主食米を使っているのは2種類に過ぎない、しかも使っているのは新米だけ
<小松酒造:小松社長さまのお話し>
「酒造業界にとって、備蓄米が入ってきても、大きな変化はないと思う」
「備蓄米でお酒を造ることが酒蔵によってはあるかもしれないが、経営に貢献するのは数%の範囲ではないか」
はっきりしたご不満は述べられていませんが、備蓄米の放出はあまり効果はないという感じを受けます
国内の酒類の市場で無許可転売?
プラミアム系の日本酒関係の商品はフリーマーケット市場で通常価格の2〜3倍の価格で取引されている状況。
飲食店、結婚式場を装った大量購入、商品の識別番号を消して、転売している悪質な業者や個人もいる模様、品質管理の観点からも最悪な状況になっています。
本来の日本酒が好きで飲んでいる人にちゃんとした製品が届くようになってほしいものです
第二、第三の米騒動
毎日の味噌汁、晩酌の日本酒、お料理に使う調味料…これらが高くなったり、手に入りにくくなったりする可能性があります。
「第二、第三の米騒動」というのは、まず主食用米が不足し、次に加工用米が不足して調味料や酒類が高くなり、最終的には米に関係するあらゆる食品が不安定になることを指しています。
昔から日本人の食生活を支えてきた味噌汁や日本酒が、贅沢品になってしまうかもしれません。
そんな心配な状況が、実は今、静かに進んでいるのです。
でも、この問題を知ることで、私たちも何か対策を考えられるかもしれませんね。
では、筆者がこの記事で書きたかった
本題に移ります
⭐️令和の米騒動はなぜ起きたのか?
令和の米騒動はなぜ起きたのか?
これには根深い問題が隠れています。
- 2023年の記録的猛暑による不作
- 一部の流通業者による在庫積み増し
- インバウンド活発による米の需要増
政府は②と主張、しかしその背景には、、、
農林水産省が把握している毎年の生産量は的確なのか?
JAはこの危機に適切な行動がとれているのか?
米の流通に透明性はあるのか?
根深い問題が横たわっています!
令和の米騒動の原因を時系列でチェック!
1942年食料管理法のもと
・戦後の食料不足の解消を目的に、米の生産から価格まですべてを国が管理していた
・政府は農家から高価格で買入→消費者に安価で販売
・それにより農家による生産業が増加→国の財政赤字が問題になる
高度成長期の1970年頃
・食の欧米化で米消費が減り、パン食に、米離れが表面化!
・政府は生産量を減らす目的で減反政策をはじめる
・農家に補助金を出し、他の作物への転作を促し、米の作付け面積を減らした
1993年GATTで決まったこと
・ウルグアイラウンドで米市場の開放を求められる
1995年ミニマムアクセス
・ミニマムアクセスの仕組みで年間77万トンの米を毎年輸入することに
・食料管理法も廃止され、民間で自由に流通させる仕組みに変わった
・減反の目的が米余り是正と価格維持へと変化した
2018年まで減反政策廃止
・減反政策は廃止されたが、現在まで事実上の生産調整が続いている状況
・かつてのような強制力は強くなく、全国の需要見通しを国が示す
・それをもとに都道府県や農協が生産量を調整する方向に変わっている
・減産だけではなく、今年(2025年)のように増産も可能
主食米の価格動向
引用元・農林水産省 相対取引価格の推移
農林水産省の資料を見ても、米の価格は昨年はじめまでは
右肩下がりで下がり続けていました。
| (消費者)😀 | (生産者)😭 |
| 安い米の価格の恩恵を受けていた | 稲作農家は利益が出ず15年間で半減 140万→70万<個人経営数> |
米の生産能力
・生産を減らし続けた結果→ 米の供給能力が弱まった
・安定していた生産が猛暑などの変動要因を大きく受けることになる
生産力が弱くなっているのが現在の米騒動の背景にある
・2023年の米の生産量661万トン
・2023年の米の需要 705万トン
△44万トンの不足
2024年 相場動向見合による流通在庫不足が発生
・米が市中に出回らなくなった
・①前年の記録的猛暑による不作
・②一部の卸売業者による在庫の積み増し
・③インバウンド需要増による米消費が増えたこと
2025年3月 備蓄米の放出
・3月から31万トンの備蓄米を放出
・高値をつけた業者が落札する一般競争入札では市中の価格は下がらなかった
備蓄米放出の手順
| 政府 →○ | 集荷業者❌→ | ←❌卸売業者 | ←❌小売 | ←❌消費者 |
| 放出 | 備蓄倉庫からJAに集約 | 手続が煩雑で手が回らない | 受発注手続が煩雑すぎる | 米が手元に届かない |
🔸JA全農から卸会社、卸会社から小売 この段階の手続きが煩雑
結果、消費者に届きにくい!
2025年5月 備蓄米の放出方法を変更(随意契約)
・政府が決めた価格で小売業者に直接売り渡す
・5月末には備蓄米が2000円代で店頭に並ぶようになった
・しかし、まだまだ潤沢ではなく、しかも銘柄米の価格は高値止まりのまま
まとめ:令和の米騒動の現在と今後
筆者は「なぜこんなに米が高くなったの?」と疑問におもっていました
いろいろ調べたら、この問題について政府の説明と現実の状況に大きなギャップがあるように感じました
政府の見解と疑問点
政府は「卸売業者が在庫を積み増ししているのが原因」と説明しています。
つまり、お米はちゃんとあるけれど、業者が溜め込んでいるから市場に出回らないということです。
もしこの説明が正しければ、政府が備蓄米を放出すれば相場が下がって、私たちの食卓にも安いお米が戻ってくるはずですよね。
でも、現実はそう簡単ではないようです。
見えてきた本当の問題
今年も猛暑予想が出されており、2025年7月現在もかなりの暑さが続いています。
お米は暑さに弱く、特に実りの時期の高温は収穫量に大きく影響します。
農林水産省が見込んでいる米の収穫量、本当に達成できるのでしょうか?
天候を相手にする農業では、計画通りにいかないことも多いのが現実です。
根本的な構造問題
実は、もっと深刻な問題が隠れています。
これまでの政府の米政策により、稲作農家は実質的に減り続けているんです。
田舎を訪れると分かりますが、お米を作っている農家の多くは高齢者です。
そして、その子どもたちが農業を継ぐケースは年々少なくなっています。
「重労働の割に収入が少ない」「将来性が見えない」といった理由で、若い人たちが農業から離れているのが現状です。
私たちが知っておくべきこと
つまり、今の米不足は単なる一時的な問題ではなく、日本の農業全体が抱える構造的な問題が表面化したものかもしれません。
政府が「業者の在庫積み増しが原因」と言っても、実際には
・猛暑による収穫への不安
・農家の減少と高齢化
・後継者不足による将来的な生産力低下
これらの問題が複合的に絡み合っているのが現実のようです。
備蓄米の放出だけでは解決できない、もっと根の深い問題があることを、私たち消費者も理解しておく必要があるかもしれませんね。

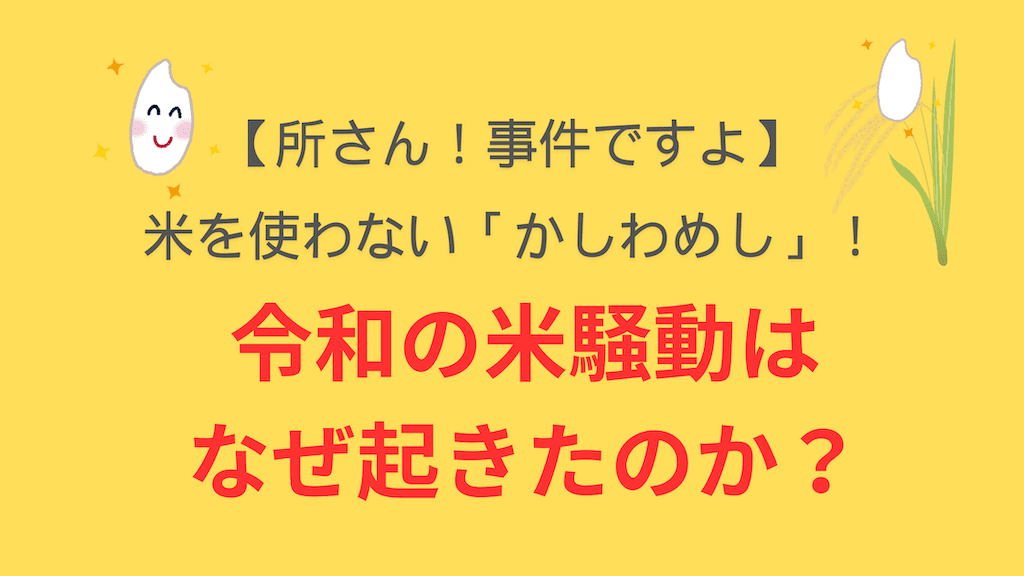

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a63451f.eec18f55.4a634520.4fffef2e/?me_id=1381599&item_id=10008752&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkojistore%2Fcabinet%2Fselect_lp%2F1129-011076.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a634ac6.20c90a16.4a634ac7.763d741c/?me_id=1391365&item_id=10000081&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnihonkaisui-urashima%2Fcabinet%2Fcompass1653631507.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a634ca2.483147c5.4a634ca3.72dbdd4f/?me_id=1303370&item_id=10029363&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenetkome%2Fcabinet%2Ftasya110%2F7266787.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)